光になりたい ~上巻~
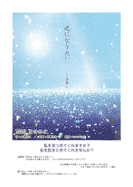 ひかりの無い世界があるとしたら、それはどんな世界だろうか…。そんなことは想像したくない。でもね、世の中にはそんな世界しか見られない人がいるんだよ。
ひかりの無い世界があるとしたら、それはどんな世界だろうか…。そんなことは想像したくない。でもね、世の中にはそんな世界しか見られない人がいるんだよ。
主人公のクラスに、ある人が転入してきた。その少女の名前は田村由梨絵。彼女は目が見えない。ただ、それだけ。他の人と違うことなんて、何一つ無い。
―――だからね、普通に生活しているんだよ。
―――そしてね、普通に恋をするんだよ。
盲目の少女、田村由梨絵と盲導犬の薫。そして、主人公を中心にさまざまな人がお互いに支え合い、成長していく…。そんな中…主人公…河口聡は田村由梨絵に恋をした…。
鈴響雪冬の書く創作恋愛小説では、はじめてのシリアス作品となる『光になりたい』。繊細な言葉で彩られる小説は、明らかに過去の作品とは異色です。
立ち読み
朝一番の太陽の光。そして、新学期が始まる今日。何もかもが何時も通りで、しかし、何もかもが新しく見える。今日から三年生になる。たったそれだけの事で、なんだか急に大人に近づいたような気がした。もちろん、やる事は沢山ある。進路の事も含め、今年は忙しくなりそうだ…。
そんなこれからの予定に頭を傾けながら、俺は朝ご飯を食べている。
「今日から新学期だな」
テーブルを挟んでの親子の会話。
「うん」
「お前も三年になるんだ、気合入れろよ」
「わかってるって。じゃ、行ってきます」
「行ってこい」
何時もの父親の声に見送られ、俺は家を出た。春と言ってもまだ空気は冷たい。自転車で風を切ると体が波打った。
教室の前に立つと、俺は中を覗き込んだ。
「ちょっと…早すぎたかな」
開け放たれたドアの向こう側…誰もいない教室には、朝日に照らされた塵が見え隠れしていた。
普段も早く学校に来るが、今回はその中でもトップクラスの時間帯だ。
「これじゃあ、電車で来てる人もまだいるわけないよな」
クラスも二年から三年に移動し、席は名簿順に戻っている。面子も変わらないのに、新任の先生のためと言う事らしい。しかし、何となく新鮮みに欠けるこの配列。
「まぁ、いいけど…」
ドアを閉めると、窓を開け、俺は自分の席に腰を下ろした。学校の喧騒を遮断し、外の音を導くため…。
軽い鞄を床に置き、その中から小説を取り出した。ページを広げ、栞を取る。視線が文字の羅列を縦に追っていく。もう少しで感動的シーン―――と言うところで、その作業はドアが開けられる音で中断された。俺は開かれた教室のドアを見る。
「なんだ、河口か。どうしたんだ? 何時もよりかなり早いな」
担任の国府田先生が立っていた。
「たまたま早く来てしまって…」
「そうか。まぁ…それじゃあ、お前には紹介しておくか。転入してくる事になった田村由梨絵さんだ」
「転入ですか?」
「あぁ。田村、教室に入れ」
そう、先生が廊下に向かって言う。
「Go」
英語の発音が聞こえ、その直後、一人の少女がドアの前に立つ。
「Ok」
外国圏の生徒だろうか。
だが、その考えは数瞬のうちにかき消される事になった。
「薫、Down」
彼女の右手にはドラマでしか見た事がない器具…ハーネスが握られている。そして、その紐の先で大人しく床に伏せているのは…ラブラドル・レトリーバー…。
「はじめまして」
俺がそう言うと、彼女は初めて俺の方を向いた。
「はじめまして…。よろしく………お願いします」
「あぁ、よろしく」
深々とお辞儀をした田村さんに俺もつられてお辞儀をしてしまう。
「彼女は見たとおり、目が見えなくてな。盲導犬を連れている」
盲導犬…。目が見えない人の道案内をし、歩行の安全を守るように訓練された犬の事だ。
「…盲導犬の、薫です。この子もよろしくお願いします…」
「あぁ、よろしく薫」
俺がそう言っても薫の方は見向きもしない。
「じゃあ、私と田村さんは一旦職員室に戻るからな。ホームルームで紹介する予定だから、まだ誰にも言わないように」
「はい」
「失礼します。薫、Door」
その言葉を残し、田村さんは教室を出ていった。
目が見えない…か…。どんな世界なんだろうな…。想像を巡らしてみるが、その世界は全く想像出来なかった…。
鐘の音と共に全員が席につく。それでも話し声がやむ事はない。もちろん、俺にも例外はない。
「よぉ、聡。元気だったか?」
「元気も何も、二週間でそんなに変わらないって」
明るい声で俺に話しかけてきたのは義之だった。
「そうか?」
俺は普通に返事をする。
「そう言うお前は、なんか変わったのか?」
「いや…」
心底つまらなそうな顔をして返事をした義之は急激に顔を変え、「そう言えば、今日転校生が来るみたいだな?」と言った。
「どうして?」
いきなり話の方向を変えた義之にちょっと戸惑いつつ、相槌を打つ。俺は義之が何故そう言う結論に至ったのかを聞く事にした。
「どうして…ってなぁ…。教室に机が一個増えていたらそりゃ転校生だろ?」
「まぁ確かに」
俺の机は二列目。義之の机は三列目にある。そして、四列目の一番後ろに机が一個増えていた。あそこが田村さんの席か…。そんな事を考えつつ俺は義之と話を続ける。
「女の子だったらいいな」
「やっぱり、そうなるのか」
「あぁ。当たり前だろ?」
「…そう言うものなのか? ここで男が転校してきて、男子一同ががっかりすると言うオチも結構あると思うけど?」
「んな、希望のない事言うなって。夢は大きく行こうぜ!」
パシッ、と俺の背中をたたいた義之は笑顔一二〇%だ。………どんな小さな希望なんだろか…。
「今日はお前らにいい話がある。特に、男どもにとってはなっ!」
国府田先生がそう言った瞬間、口笛の嵐が巻き起こる。元から騒がしかったクラスは、既にお祭り状態だ。このままリオのカーニバルに連れて行きたくなるぐらい…。
なんなんだろうな…このクラス。まとまりがないようでいて、こう言う時には何故かまとまりがある。去年の文化祭だって、直前まで内容が決まらなかったのに、突然、はりきって作業を始めて、結局展示部門で優勝してしまったし…。
「それじゃあ、紹介するぞ。転入生の田村由梨絵さんだ」
作品について
- 作者
-
- 企画: 鈴響雪冬
- 著作: 鈴響雪冬
- 冊子
-
- 大きさ: B5
- ページ: 表紙込み64P / 本編51P
- 文字数: 約5万5000文字 (原稿用紙188枚相当)
- 価格: 300円
- 印刷: レーザープリンタ (表紙のみインクジェット)
- 表紙: 総天然色 / インクジェット用紙・厚口
- 本文: 黒一色 / 上下二段組み / 色上質
- 製本: 並製本・平綴じ
- 発行: 2003年12月23日
- 重さ: 160グラム
- 備考
-
- 登場人物紹介有り
- 通販略称: 光に・上
- EYEマーク
- 本文用紙に、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用